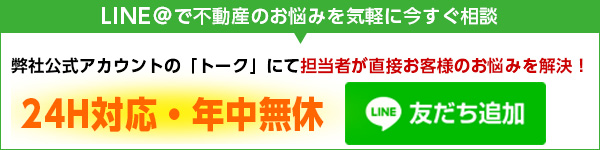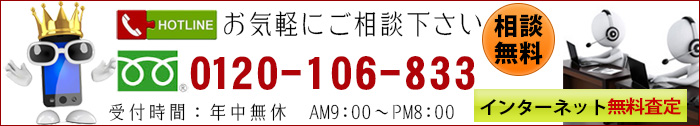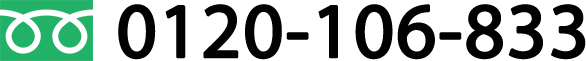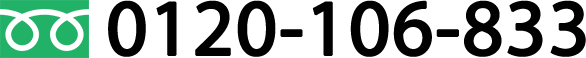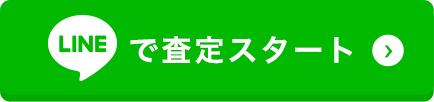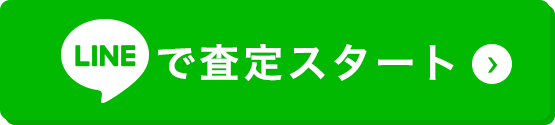不動産の「引取サービス」について
- 新着情報
- 2025/05/02
所有者が「お金を払って引き取ってもらう」
新しい不動産取引の形──国土交通省が示す“引取サービス”とは?
「空き家を相続したけど、ボロボロで売れない…」「税金だけ毎年払い続けている使っていない土地がある」「業者に相談しても“再建築不可だから買えない”と断られた」──そんな声をよく耳にします。これまでは不動産は「売ってお金になる資産」とされてきましたが、今の日本では「手放したいのに誰も引き取ってくれない」というケースも増えています。
こうした背景を受けて、国土交通省は2024年、新たな不動産取引の形として「引取サービス」に関する調査・発表を行いました。本記事では、その内容をわかりやすく解説しつつ、空き家・空き地・老朽物件を抱える方にとってどのようなメリットがあるのかを探っていきます。
■ 引取サービスとは?
「引取サービス」とは、不動産の所有者が一定の金額を支払い、事業者がその不動産を“引き取る”という新しい取引の形態です。
これまでの不動産取引は「売買」が基本。つまり、所有者が不動産を売り、買主が代金を支払うという流れでした。しかし、空き家の増加や老朽化によって「買いたい人がいない」「建物の解体費がかかる」「権利関係が複雑で再利用しにくい」など、売却が非常に困難なケースも多くあります。
そんな時に登場するのが「引取サービス」。売れない不動産を“お金を払ってでも手放したい”という所有者のニーズに応える仕組みなのです。
■ なぜこのサービスが求められているのか?
日本の空き家は2023年時点で約900万戸、実に7戸に1戸が空き家という時代に突入しています。放置された空き家は景観の悪化、近隣トラブル、防災リスクの原因にもなります。また、固定資産税や管理費の負担は所有者にのしかかり、「誰も住まない、使わない、売れないのに持っているだけで損をする」という状態に。
こうした空き家問題を解決する一つのアプローチとして、引取サービスが注目されているのです。
■ 国土交通省の調査結果と現状
国交省の調査によれば、現在、全国で59社がインターネット上で「不動産引取サービス」を提供しており、そのうちの約64%(38社)が宅建業者。地域別では、東京・大阪など都市部に多くの業者が存在しています。
ただし、法制度が未整備であることから、「金銭を支払って引き取ってもらったが、名義変更がされない」「引き取り後にトラブルがあった」などのリスクも懸念されています。
そこで国土交通省は、次のような課題を挙げて制度整備を進めています。
■ 引取サービスの3つの課題
-
取引の安全性の確保
所有者が支払いをした後、事業者が名義変更を行わず放置されるリスクなど、トラブル防止の仕組みが必要です。 -
適正価格の維持
「本当は売れるかもしれない物件」が安易に引取サービスに回らないよう、適正価格での流通機会を奪わない配慮も求められます。 -
引取後の管理体制
事業者が引き取った不動産の管理責任や再利用のルールも重要なポイントです。放置されれば、所有者が変わっても問題は解決しません。
■ 空き家所有者にとってのメリットは?
現実問題として、「売れない不動産」を抱えている方にとって、引取サービスは大きなメリットがあります。
-
不動産の維持管理から解放される
-
固定資産税の負担がなくなる
-
売却活動や煩雑な手続きが不要
-
相続した空き家を短期で手放せる
たとえば、古くなった長屋や再建築不可の戸建、私道に接している土地、荷物が残ったままの空き家など、通常の市場ではなかなか流通しにくい物件が対象となります。
■ まとめ「売れない」と思っても、選択肢はある
不動産の価値は「売れる・売れない」だけで決まるものではありません。マイナス評価の多い物件でも、活用法次第で価値が生まれることがあります。国が引取サービスに注目している背景には、「放置されるより、引き取って再活用してほしい」という社会的な目的もあります。
空き家や空き地、長屋、相続物件、老朽化した収益物件──「売れない」とあきらめる前に、まずは一度、こうした新しいサービスや専門業者に相談してみることをおすすめします。
マイダスでも、関西エリア(大阪・奈良・兵庫)を中心に、空き家・空き地・長屋・相続不動産・荷物あり物件・他社で断られた不動産などの買取を行っています。
相談・査定・見積はすべて無料。再利用や収益化の視点からもご提案が可能です。
「もうどうにもならない」と思っていた不動産が、次の一歩に変わるかもしれません。
まずはお気軽にご相談ください。
※弊社規定により買取できない場合もございます。
予めご了承ください。