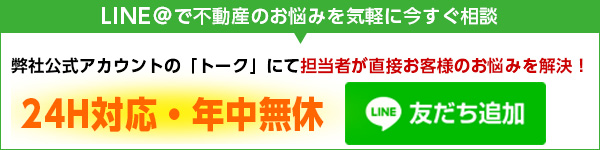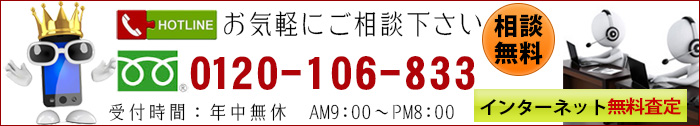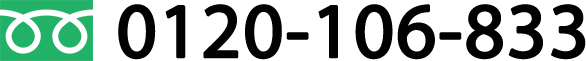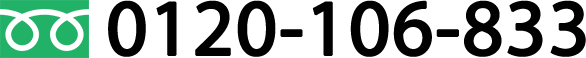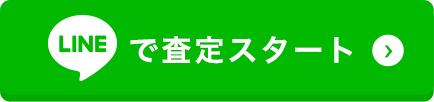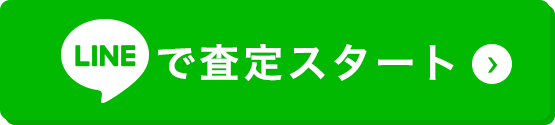所有するだけで損をする?「負動産」にしないための賢い不動産戦略
- 新着情報
- 2025/09/13
不動産は「負動産」に変わる時代
かつて日本の不動産は「資産」として、所有しているだけで価値が上がると考えられていました。
しかし、今の日本ではその常識は通用しません。
所有しているだけで税金や維持費がかかり、売ることも貸すこともできない「負動産」が増えているのです。
なぜ、このような事態が起きているのでしょうか?
最大の要因は、日本の人口減少と少子高齢化です。今後、35年ローンで家を購入した人がローンを払い終える頃には、日本の人口は激減し、社会構造も大きく変化しているでしょう。
不動産価格を決める「需要」と「供給」
不動産の価値は、シンプルに「買いたい人がどれだけいるか(需要)」と、「売りたい家がどれだけあるか(供給)」のバランスで決まります。
-
需要の減少:人口減少により、家を買う人が減っています。さらに、社会保障負担の増加で実質的な所得が減り、家を買う力が低下しています。
-
供給の過剰:需要が減っているのに、新築住宅はどんどん建てられています。この結果、空き家が急増し、今後さらに深刻な問題になると予測されています。
需要が減り、供給が減らない状況では、不動産の価値が下がるのは自然な流れです。
「負動産」になる前に、不動産をチェックしよう
すべての不動産が「負動産」になるわけではありません。
価値を保つ不動産は、**「立地の良さ」**にあります。駅からの距離、周辺施設の充実度、治安の良さなど、多くの人が住みたいと思う場所の不動産は、今後も需要を維持できるでしょう。
逆に、価値が下がりやすい「負動産」とは、需要が低い「ニーズのない土地」にあるものです。
特に注意が必要なのが、災害リスクが高いエリアです。
近年、ゲリラ豪雨や地震など、自然災害のリスクはますます高まっています。
そのため、家を探す人は、事前にハザードマップなどを確認し、リスクの高い土地を避ける傾向にあります。
これから不動産を購入しようと考えている方は、以下のポイントを参考に、物件の価値が下がるリスクを事前に調べておきましょう。
価値が下がりやすい不動産のチェックポイント
-
居住誘導区域外:自治体が都市計画で「住む場所ではない」と指定したエリアは、将来的にインフラや生活サービスが縮小される可能性があります。
-
災害リスクの高い区域:土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)、津波災害特別警戒区域(オレンジゾーン)、浸水想定区域など、ハザードマップでリスクが指摘されている場所は、将来的な売却が困難になる可能性があります。
-
市街化調整区域:原則として建物の建築が許可されていない区域です。
-
急傾斜地崩壊危険区域・地すべり防止区域:がけ崩れや地すべりの危険性が高い場所で、建築が制限されます。
賢い不動産選びのポイント
これから不動産を購入するなら、「資産」として価値を維持できるか、将来の売却や賃貸を視野に入れているか、慎重に検討することが重要です。
そのためには、ハザードマップや都市計画情報をしっかりと確認しましょう。
住みたい場所がどのような区域に指定されているか、どのようなリスクがあるかを把握することで、将来「負動産」を所有してしまうリスクを避けられます。
不動産は人生で一番大きな買い物の一つです。目先の価格だけでなく、将来的な価値まで見据えて、賢い選択をすることが大切です。
あなたが住もうとしている場所は、本当に「負動産」になりませんか?
マイダスでは、関西エリア(大阪・兵庫・奈良など)を中心に、相続した不動産の問題に対応しています。
無料相談・現地調査も承っておりますので、「手放したいけどどうすればいいか分からない」とお悩みの方は、ぜひ一度ご連絡ください。
株式会社マイダス|相続した不動産の再生・引取サポート
【大阪・兵庫・奈良など対応】
空き家・負動産・引取・共有持分整理・再販再生